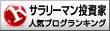歴史
クリストファー・マクドゥーガル 訳・近藤隆文 NHK出版 2015.8.30読書日:2024.2.7 「BORN TO RUN」で、人間はもともと走るようにできていることを語った著者が、その他に人間がもともと持っている野生の能力をクレタ島の人たちの身体能力を中心に語った…
ロバート・ダーントン 訳・上村敏郎、矢谷舞、伊豆田俊介 みすず書房読書日:2024.2.8 フランス、英領インド、東ドイツの検閲の実際を調べて、検閲とはなにか、検閲官はどんなふうに検閲という仕事に関わったのか、ということを比較した本。 ロバート・ダー…
養老孟司 ✕ 茂木健一郎 ✕ 東浩紀 講談社 2023.9.20読書日:2024.1.16 日本は生きづらい国であり、それは日本の歪みに由来するのではないかと、三人の賢人が鼎談する本。 三人が考える日本の歪みとはなにかについては、目次から明らかである。「先の大戦」「…
小熊英二 講談社 2019.8.1読書日:2023.12.19 デモなどの社会運動が好みという社会科学者の小熊英二が、ギリシャ時代からの哲学を振り返り、運動をして本当に社会が変わるのか、ということを述べた本。 日本の学者ってものすごく頭が良いと思う。教養や学術…
高野秀行 文藝春秋 2023.7.30読書日:2023.11.23 チグリス・ユーフラテス川の河口の湿地帯はメソポタミア文明が興った地域であるが、5千年の昔から現在に至るまで敗れた者や迫害された者が逃げ込む地域でもあり、辺境作家の高野秀行が中国の水滸伝になぞら…
鈴木雄一郎 講談社 2019.6.1読書日:2023.10.31 私鉄の電鉄は都市と郊外とを結んで、郊外では住宅地を売り、住宅地の通勤、通学の客を運ぶことをビジネスモデルにしていると思われているが、鉄道を作った最初のビジネスモデルでは寺社を中心とした参詣と物見…
ジョージ・ダイソン 監訳・服部桂 訳・橋本大也 早川書房 2023.5.20読書日:2023.10.7 ライプニッツの唱えたデジタルの世界が現在あふれているが、今後はアナログの世界が復権するという主張をする目論見に無理やり自分の体験を組み込んだ本。 デジタルから…
三崎律日 KADOKAWA 2019.8.23読書日:2023.8.23 ニコニコ動画で配信した「世界の奇書をゆっくり解説」をまとめた、世界の奇書に関する本。 副題の通り、歴史を動かした本から、これも奇書?というような本も含まれている。たとえばコペルニクスの「…
カール・エリック・フィッシャー 監修・松本俊彦 訳・小田嶋由美子 みすず書房 2023.4.10読書日:2023.7.6 本人のアルコール依存症との戦いを交えて、アメリカの依存症対策の歴史を述べた本。 なんかアメリカの政策って極端すぎる気がする。アルコールについ…
最近読んだエマニュエル・トッド「我々はどこから来て、今どこにいるのか」と柄谷行人「力と交換様式」などを読み比べて、未来の社会がどうなるのか考えてみたい。 「我々はどこから来て、今どこにいるのか」から次のようなことを学んだ。 家族の形式が社会…
柄谷行人 岩波書店 2022.10.5読書日:2023.3.8 人類の歴史はその交換様式で区別でき、そのスタイルは4つしかなく、いまは商品や権力に関連した交換様式が強いが、将来は個人に関係した交換様式の世界になると主張する本。 最初はそれがどうしたという感じで…
水木しげる 講談社文庫 2022.7.15読書日:2023.2.27 (ネタバレあり 注意!) 水木しげるが体験したパプアニューギニア、ニューブリテン島での戦いを一兵士の視線で描いたもの。 「のんのんばあとオレ」が印象深かったので、水木さんの代表作を読んでみたも…
エマニュエル・トッド 訳・大野舞 文藝春秋 2022.6.20読書日:2022.12.25 歴史人口学者のエマニュエル・トッドが、ウクライナ戦争は米英により仕掛けられた事実上の第三次世界大戦だと主張する本。 エマニュエル・トッドのことは知っていたが、これが初めて…
ムーギー・キム 東洋経済新報社 2022.7.14読書日:2022.12.23 グローバル・エリート・ビジネスマンで在日3世のムーギー・キムが、日本と韓国の関係をその根本から真剣に考えた本。 ムーギー・キムってもう40代なんだそうだ。いまでは起業家として香港に住ん…
ニーアル・ファーガソン 訳・柴田裕之 東洋経済新報社 20220.6.2読書日:20220.9.23 人類が経験した大惨事のほとんどがパンデミックであり、大惨事はべき乗分布のロングテールに存在するので予測は不可能であり、我々ができるせめてもの目標は大惨事が起きて…
井上章一 朝日新聞出版 2022.5.30読書日:2022.9.10 明治になって洋装が普及したものの下着はふんどしのままであり、戦後も1960年ぐらいまではふんどしが残っており、ふんどしはどうしてこんなに長く残ったのかを考察する本。 女性の下着のズロースが普…
トーマス・セドラチェクの「善と悪の経済学」を読んで感銘を受けたことに、ユダヤ人の独自性がある。 わしはもともとユダヤ人は独自性があると思っていたが、そこは宗教の一神教における神との関係に限定されると思っていた。つまり、次のようである。 ある…
トーマス・セドラチェク 訳・村井章子 東洋経済新報社 2015.6.11読書日:2022.5.13 経済学は倫理学から出発したのに、そのルーツを忘れて数学のみを語る学問になってしまっているが、倫理という魂をもう一度取り入れ、人の限りない欲望を抑えるような学問に…
「世界を貧困に導くウォール街を超える悪魔」を読んでわかったのは、結局のところ、例外の場所や制度を利用して、税金を納めることなしに利益を搾り取って行く金融産業の姿だった。 これを読んでわしが思い出したのが、フリーポート(保税倉庫)と呼ばれる、…
ニコラス・ジャクソン 訳・平田光美、平田完一郎 ダイヤモンド社 2021.11.2読書日:2022.3.20 金融業が国の経済の中心になると、国民になんの利益ももたらさず、かえってその国の経済を衰退させ、国民を貧困に陥れると主張する本。 この本で書かれているのは…
ルトガー・ブレグマン 訳・野中香方子(きょうこ) 文藝春秋 2021.7.30読書日:2022.1.20 オランダの革新的なジャーナリズムプラットフォーム「デ・コレスポンデント」の創設者のひとりである歴史家、ジャーナリストのブレグマンが、人類は基本的に善である…
兵頭二十八 草思社 2012.3.26読書日:2022.1.10 押井守が愛読している人らしいので、とりあえず良さげなものを選んでみた。2012年の出版と10年前であり情報は古いが、しかしそこに書かれていることが正しかったかどうかを判断するにはちょうどいいかも…
遠藤誉 ビジネス社 2021.4.1読書日:2021.12.22 遠藤誉が、鄧小平がいかに陰謀にまみれた政治家であり、多数のライバルを陥れてその成果を横取りしたかを記し、習近平の父親、習仲勲(しゅうちゅうくん)もその犠牲になり、習近平はいまトップとなって鄧小平…
ジャック・アタリ 訳・林昌宏 プレジデント社 2021.9.16読書日:2021.12.16 ジャック・アタリが、過去にメディアに起こったことは未来でも同じことが起こるに違いないから、このままテクノロジーが進むと恐るべき未来が訪れる可能性があるとし、いますぐ行動…
ショシャナ・ズボフ 訳・野中香方子(きょうこ) 東洋経済新報社 2021.7.8読書日:2021.11.28 現代の巨大IT企業(主にグーグル、フェイスブック)は人間の情報をすべて集めてそこから利益をとるだけでなく、精神すらもコントロールしようとする邪悪な存在…
ブランコ・ミラノヴィッチ 訳・西川美樹 解説・梶谷懐 みすず書房 2021.6.16読書日:2021.11.22 共産主義を含め、すべての経済システムは資本主義を目指していたと主張し、現在は米国を中心とした「リベラル能力資本主義」と中国を中心とした「政治的資本主…
佐藤航陽(かつあき)ディスカヴァー・トゥエンティワン 2015.8.30読書日:2021.11.21 メタップスの創業者の佐藤航陽が、未来は一定のパターンで変化すると主張し、意思決定するにはこのパターンにあっているかどうかで思考し、その意思決定を実行に移すとき…
須川邦彦 青空文庫 2004.5.8 (底本 新潮文庫 2003.7.1、親本 講談社 1948.10)読書日:2021.10.10 明治32年、漁場の調査に出た龍睡丸(りゅうすいまる)がハワイ列島のパール・エンド・ハーミーズ礁近海で遭難し、乗組員16人がひとりの死者も出さずに無…
「新ジャポニズム産業史」を読んで思い出した小ネタを書く。 たぶんほとんどの人はこの本を読めば自分はどうだったかな、と考えるんじゃないだろうか。そしてなにか思い出すのではないだろうか。 わしはポケットモンスターのアニメについて読んでいて、ちょ…
マット・アルト 訳・村井章子 日経BP 2021.7.26読書日:2021.9.19 80年代のアメリカで日本の文化に耽溺して成長した著者が、戦後の日本文化がいかに世界、特にアメリカに影響を与えてきたかを検証した本。 いちおう2020年まで書かれているけど、中身の…