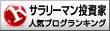アナニヨ・バッタチャリヤ 訳・松井信彦 みすず書房 2023.9.19
読書日:2024.3.21
ハンガリー出身の数学の天才で、数学の力を量子力学、コンピューター、ゲーム理論、AIなど、純粋数学の枠を越えて貢献し、手がけた分野のすべてがその後大きく発展して、いまだに現代に大きな影響を及ぼして、未来から来た男と呼ばれたジョン・フォン・ノイマン(1903ー1957年)の評伝。
わしはなぜかジョン・フォン・ノイマンとクロード・シャノンをごっちゃにしてしまう。どちらも情報工学に関係があるからだろう。今回ジョン・フォン・ノイマンの評伝を読んだから、あとはシャノンの伝記を読めば、もうごっちゃになることはないだろう。
ノイマンは数学者なんだけど、数学者におさまらないところがあって、数学以外の分野にも詳しい。子供のころに家にあった分厚い歴史書を読んで、ほとんど暗記してしまっている。だからこれから起きる歴史の流れがはっきり見えていたんだろう。歴史の展開の見通しも完璧で、故郷のハンガリーから婚約者を第2次世界大戦の直前に脱出させたりしている。この辺の見極めは、ぐずぐずしてひどい目にあった他のユダヤ人や上流階級の人たちとは異なっていた。
ノイマンは全体主義や共産主義を嫌っていた。そして当時は、ナチスドイツやソ連といった、どうしても負けるわけにはいかない相手がいたのだ。それで、原爆や水爆の設計にいそしんだ。爆発でプルトニウムを集中させる爆縮の設計をしたし、核爆発で核融合を起こす水爆の基本構成を示した特許も書いている。
爆縮の設計のためにコンピューターが必要になると開発を強力に進めた。コンピューターというものがなかった時代に、処理装置(CPU)とプログラムとメモリと入出力装置からなるノイマン型という構成を考え出している。いまこの文章を書いているコンピューターも、普段使っているスマートフォンもノイマン型のコンピューターだ。ここで大事なのは、この構成だけでうまくいくということを、ノイマンが数学的に証明していることだ。(同時に限界も理解している。)なので、自信をもって開発することができた。あるアイディアがどこまで普遍的に使えるかを正確に見通すことができる人なのだ。
そしてコンピューターを考え出すと、すぐにそれが人間の能力を追い越すことも理解している。コンピューターが人間の知能を追い越すことを「シンギュラリティ(技術的特異点)」というけれど、この言葉を初めて使ったのはノイマンなんだそうだ。ものすごい先見性がある。
安全保障の分野で有名な研究所にランド研究所があるけれど、マンハッタン計画の影響で誕生したこの研究所にもノイマンはかかわっている。もちろん核戦略の立案関係なのだが、必要だったのはテクノロジーの知識だけではなく、ノイマンの開発したゲーム理論だった。ソ連という異質の相手にどのように戦略を組めばいいのか、ゲーム理論が役に立ったのだ。
ノイマンは論理を使う学問について全般的に何でもできる人で、物理のような数学をつかう分野ではもちろんだが(量子力学のハイゼンベルグの行列式とシュレディンガーの波動方程式は原理的に同じであることを示している)、ゲーム理論を使った経済学の本も書いている。
ゲーム理論も興味深いかもしれないが、それ以上に経済学で効用のスコア(例えば人の満足度のこと)という基本概念を作ったというほうが興味深い。そのためのユーティルという単位まで作った。驚いたことにノイマンが経済について考えるまでに、このような効用を数値化するという発想はなかったのだそうだ。このノイマンの発想の結果、経済学は効用を数値で表せられるようになり、いろんな計算に使われるようになり、合理的とかそうでないとかという議論が数字でできるようになった。わしはノイマンの単純な効用の数値化に疑問を感じるけど、計算できるようになったのは確かで、結果、ゲーム理論は電波の周波数オークションの設計に欠かせないのだという。なるほどね。
結局、ノイマンがやったことというのは、世界を単純なモデルで還元して考えたということなのだろう。しかもノイマンはその単純なモデルがどこまで有効かも数学的にすっかり把握していた。限界はあるのだけど、その単純なモデルでも有効範囲は広く、彼は見通せられる範囲を極限値まであっという間に見通したわけだ。
その真骨頂を表しているのが最後の仕事となったオートマトン理論だろう。ここで彼は生物を単純なモデルで表そうとしたのだ。生物を座標において、移動やコピーを作るという単純なルールを3,4行の少ないプログラムで書く。このプログラムを膨大な回数繰り返すと、複雑だが特徴あるパターンが生まれることがある。ノイマンはいくつかの基本的なルールを繰り返すことで、知性のある生命だって生まれると考えたわけだ。なるほど。これならマンデルブローの複雑系の科学に理解を示したのも納得だ。
ノイマンは意外に純粋数学への貢献は少ない。たぶん世の中の先を見通す力が強すぎて、純粋数学では物足りなかったのだろう。このころは数学の限界もいろいろ明らかになったことも関係しているのかもしれない。ノイマンがまいた種はいろいろな分野で大きな研究分野に育っている。未来から来た男というあだ名はだてじゃない。
ガンによって50代で亡くならなければもっと人類に貢献してくれたんだろうけどねえ。
アナニヨ・バッタチャリヤの文章は、各領域の学問について、適度に好奇心を満たしてくれるストレスの少ない文章で、とてもよかった。これだけの範囲を明快に説明するなんて、なかなか稀有な才能です。
****メモ****
・爆縮のシミュレーションは、モンテカルロ法(粒子の動きを一定時間ごとにランダムに割りふる方式)だったそうだ。世界初のコンピューターシミュレーションがモンテカルロ法だったとは。このとき、ランダムな数値を作る方法も考案している。
・ソ連が核兵器を作る前、ノイマンは先制核攻撃を主張していたそうだ。ソ連が核兵器を得る前につぶすべきだと考えたのだ。しかし、ソ連が開発に成功したことを知ると、ゲーム理論の人らしく、先制攻撃が無意味になったと理解して、その主張をやめた。しかし世間では逆に先制攻撃論が盛んになったそうだ。
・ノイマンはお金が大好きだった。純粋数学の世界にあまりいなかったのも、お金を稼ぐのが好きだったことも一因らしい。まあ、だからアメリカ社会にはとてもよくなじんだ。生まれはハンガリーの上流階級で、大きな屋敷に住んでいた。はじめてアメリカに来た時、アメリカの住宅事情に、こんなところで数学はできない、とこぼしていたそうだ。後半生では、国家的重要人物となっていたノイマンは、アメリカ中を軍用機で飛び回っていたそうだ。お金が好きだったが、コンピューターの知識を独占しようとかそういうことはしなかった。
・機械の知能と人間の知能の違いについても、すぐに人間の脳は超並列型の計算機だということを理解して、指摘している。
★★★★☆