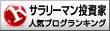読書録
アナニヨ・バッタチャリヤ 訳・松井信彦 みすず書房 2023.9.19読書日:2024.3.21 ハンガリー出身の数学の天才で、数学の力を量子力学、コンピューター、ゲーム理論、AIなど、純粋数学の枠を越えて貢献し、手がけた分野のすべてがその後大きく発展して、い…
ジョン・スコルジー 訳・内田昌之 早川書房 2023.8.15読書日:2024.3.17 (ネタばれあり。注意) パンデミックで職を失いフードデリバリーをしていたジェイミーが、偶然得た仕事は、パラレルワールドのもう一つの地球で怪獣を保護する仕事だったが……というお…
ウォルター・アイザックソン 訳・井口耕二 文藝春秋 2023.9.10読書日:2024.3.13 著名人の伝記を次々発表するウォルター・アイザックソンの最新作であるイーロン・マスクの伝記。 ウォルター・アイザックソンといえば、著名人の伝記を次々発表していて、いち…
岩尾俊兵 光文社 2023.10.30読書日:2024.3.4 日本発の経営戦略がアメリカ経由で逆輸入され、もともと持っていた経営戦略を日本企業が捨てている現状を憂え、日本自身が世界に広めなければいけないと主張する本。 日本で流行っているアメリカ由来の経営戦略…
逢坂冬馬 早川書房 2021.11.25読書日:2024.2.21 (ネタバレあり。注意) 第2次世界大戦、モスクワ近くのイワノフスカヤ村にドイツ軍が現れ、村人が虐殺される。一人、生き残った少女セラフィマは、もと女性狙撃兵イリーナに導かれ、狙撃兵として訓練を積み…
ジョエル・コトキン 訳・寺下滝郎 解説・中野剛志 東洋経済新報社 2023.11.14読書日:2024.2.24 一握りの超富裕層が世界の富の大半を握り、グローバル社会のなかで中流層は没落してデジタル農奴となり、このような状態が世襲化して引き継がれる結果、社会的…
養老孟司 聞き手・鵜飼哲夫 中央公論社 2023.11.25読書日:2024.2.25 養老孟司が自分の過去を振り返った語り書きの自伝。 養老孟司って、わしにとっては「バカの壁」で突然出てきた人のように見えていたけど、なぜ東大の解剖学の先生がこんな感じで世の中に…
川上弘美 講談社 2023.8.22読書日:2024.2.4 アメリカからの帰国子女の作家、八色朝見が、アメリカ時代の友人たちとゆるく長い付き合いを続けながら、老境にいたる心境を綴ったもの。 小説としては、初・川上弘美である。エッセイは「私の好きな季語」という…
ルーシー・ワースリー 訳・大友香奈子 原書房 2023.12.25読書日:2024.2.23 遺族が提供した資料を交えたアガサ・クリスティの最新評伝。 母親がミステリ好きだったこともあって、わしの実家には結構ミステリがあったので、アガサ・クリスティももちろん読ん…
長嶺超輝 幻冬舎 2007.3.30読書日:2024.2.18 裁判所の傍聴マニアが、裁判官の印象に残ったお言葉をまとめた本。 爆笑と書いてあるけど、それはほとんどない。いくつかクスッと笑えるものがあるだけだ。裁判なんておおむね深刻な状況だから、そもそもそんな…
クリストファー・マクドゥーガル 訳・近藤隆文 NHK出版 2015.8.30読書日:2024.2.7 「BORN TO RUN」で、人間はもともと走るようにできていることを語った著者が、その他に人間がもともと持っている野生の能力をクレタ島の人たちの身体能力を中心に語った…
デヴィッド・グレーバー デヴィッド・ウェングロウ 訳・酒井隆史 光文社 2023.9.30読書日:2024.2.17 農業の始まりが私的所有と不平等を生み、ヒエラルキーが形成され、都市や国家を生んだというビッグヒストリーの思い込みを破壊し、近年の考古学や人類学の…
ロバート・ダーントン 訳・上村敏郎、矢谷舞、伊豆田俊介 みすず書房読書日:2024.2.8 フランス、英領インド、東ドイツの検閲の実際を調べて、検閲とはなにか、検閲官はどんなふうに検閲という仕事に関わったのか、ということを比較した本。 ロバート・ダー…
坂本貴志 講談社 2022.8.20読書日:2024.1.28 定年後、収入は大幅に減るが同時に支出も減るため生活には困らず、月に数万〜10万円程度の追加収入があれば趣味をおおいに楽しむことができ、ストレスがほぼないため幸福な生活を送る人が大半だと報告する本。…
イーサン・クロス 訳・鬼沢忍 東洋経済新報社 2022.12.4読書日:2024.1.26 頭の中では自分の言葉が常に聞こえているが、その声がネガティブなループに入り脱け出せなくなったときをチャッターと名付け、どうすればチャッターから抜け出せるかを指導する本。 …
飯田一史 平凡社 2023.6.15読書日:2024.1.22 2000年代に入ってから中学生の読書は増えており、読書離れとは言えない状況であり、さらに読書の内容も以前と異なりラノベ中心ではなくなっていることを報告した本。 読書が急回復している背景は、「朝の読…
佐々木良 万葉社 2023.7.21読書日:2023.1.21 人気となった「愛するよりも 愛されたい 令和言葉・奈良弁で訳した万葉集①」の続編。 今回は聖徳太子と飛鳥京の時代が中心だそう。聖徳太子の歌が1首だけ載ってるんだって。それがこれ。 家ならば 妹(いも)が…
アレハンドロ・ホドロフスキー 訳・青木健史 文遊社 2012.10.25読書日:2024.1.18 映画、演劇、芸術などの分野で活躍する奇才のアレハンドロ・ホドロフスキーが、スピリチュアルな世界を探求し、リアリティが目に見えないところで繋がっているという、現実が…
養老孟司 ✕ 茂木健一郎 ✕ 東浩紀 講談社 2023.9.20読書日:2024.1.16 日本は生きづらい国であり、それは日本の歪みに由来するのではないかと、三人の賢人が鼎談する本。 三人が考える日本の歪みとはなにかについては、目次から明らかである。「先の大戦」「…
草薙龍瞬 KADOKAWA 2015.7.27読書日:2024.1.14 心は常に何かに反応しているが、そのほとんどは実際にはムダなもので、ムダな反応をしないようにすれば悩みがなくなり心が軽くなると主張する本。 この本は2015年の本だが、未だに売れ続けているベストセ…
永野彰一 クロスメディア・パブリッシング 2022.12.1読書日:2024.1.12 全国の空き家を100万円以下、できれば1円で手に入れてリフォームすれば、自分が住んでも良いし、貸しても良く、3件以上持てば累積的に資産が増えて一生の財産になると主張する本。…
立原透耶[編] 新紀元社 2023.12.13読書日:2024.1.19 (ネタバレあり。注意) 中華SFのマニア向けのアンソロジー15編。 やっぱり今1番面白いSFは中国かもしれない。読んでいて感心した。21世紀に入って大きく発展した中国の、科学に対する楽観的…
カール・へラップ 訳・梶山あゆみ みすず書房 2023.8.10読書日:2024.1.10 アルツハイマー病は、脳に蓄積したアミロイドが原因とするアミロイドカスケード仮説が根拠不確かなままにセントラルドグマ化して、この仮説以外は認められない状況が続き、治療方法…
リー・アンダーツ 河出書房新社 2023.9.30読書日:2024.1.8 発達障害でまともに生活できない母を、死ぬまでの2年間手助けしたことをつづった本。 痴呆になると生活能力はなくなり介護が必要になるけど、発達障害の場合はなんか微妙だ。いろんなケースがある…
アルテュール・ブラント 訳・安原和見 筑摩書房 2023.7.30読書日:2024.1.2 ヒトラー総統の官邸にあり連合軍の空爆により破壊されたと思われた馬の彫刻が、70年後の2015年に発見された経緯を述べた本。 美術界は魑魅魍魎の世界で、有名な作品が、今ど…
河合雅司 講談社 2022.12.20読書日:2023.12.26 日本では少子高齢化で人口が減るという状況なのに、それに対する備えができていないとし、実際に何が起きるのかをリアルに予想し、企業が進めるべき未来の戦略を提示した本。 2部構成になっていて、第1部で…
アレックス・ロス 訳・井田光江 早川書房 2023.4.20読書日:2023.12.25 社会契約とは、企業、政府、市民の三者で社会にバランスをもたらすための約束であるが、いまほとんどの国でそのバランスが崩れており、2020年代の選択が重要になっていると主張する…
久坂部羊 講談社 2022.4.1読書日:2023.12.21 医者で作家の久坂部羊(くさかべよう)が、人が死ぬということのリアルを教えてくれる本。 人が死ぬときに立ち会うと、医者でも最初は動揺するんだそうだ。しかし、場数を踏んでいくうちに慣れてくるという。不…
小熊英二 講談社 2019.8.1読書日:2023.12.19 デモなどの社会運動が好みという社会科学者の小熊英二が、ギリシャ時代からの哲学を振り返り、運動をして本当に社会が変わるのか、ということを述べた本。 日本の学者ってものすごく頭が良いと思う。教養や学術…
間寧 作品社 2023.6.20読書日:2023.12.19 トルコの公正発展党(AKP)のエルドアンは2002年に政権を取って以来、20年以上に渡って政権を保持しているが、なぜそれが可能だったのかについて、後光力、庇護力、言説力が優れていたからだと主張する本。…