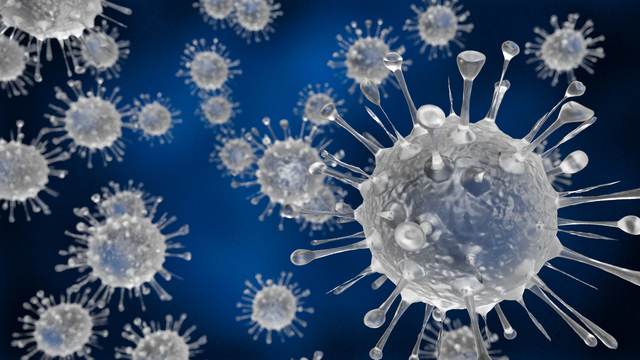ウォルター・シャイデル 訳・鬼澤忍・塩原道緒 東洋経済新報社 2019.6.20
読書日:2020.4.19
人類は農業が始まって以来、不平等な状態が定着しており、これまで平等化が起きたのは圧倒的な暴力によってでしかなく、今後は圧倒的な暴力は望みにくいので、新しい平等化の方法が必要と主張する本。
シャイデルによれば、狩猟採集を行っていたころの人類は平等だったらしい。そもそも、常に移動している身では財産は持ち歩ける以上にはなりえないし、取ったものを長く蓄えることはできなかった。そういうわけで人類に不平等が生まれるのは、定住して財産が蓄えられるようになってから、すなわち農業が起きてからだという。
農業が始まって、はじめて余剰(自分だけで使いきれないもの)というものができ、この余剰を多く持っている者と少なく持っている者に差が生まれた。余剰を持っているものは、その余剰を投資することが可能だ。例えば、新しい土地と交換することができる。それによりさらに多くの作物を得ることができるが、それはすべて余剰で、その分さらに余剰は増える。すると、それをさらに投資して、ますます余剰を集めることができる。こうして余剰、あるいは余剰を生み出す土地が一部の人間に集まるようになり、不平等が生まれる。
この不平等化の傾向は非常に強力で、余剰がある限りは自然発生的に生じてしまう。では、人類の歴史で、このような不平等が平等の方向に傾くときはなかったのかといえば、あったのである。それをシャイデルは、戦争、革命、崩壊、疫病に求め、この4つを平等の四騎士と呼んでいる。
戦争の例で上げられるのは、なんと日本である。日本は総力戦の太平洋戦争で負けた時に、ほぼ全員が等しく貧乏になった。土地は占領軍により強制的に取り上げられ、小作人に分配された。日本はこれまでにないくらい平等になって、戦後の世界に入ったのである。
日本だけでなく、第1次世界大戦や第2次世界大戦に参加した国は、どの国も多かれ少なかれ平等化が進んだ。負けた方だけではなく、勝った方も平等化が進んだ。これらの戦争は国をあげた総力戦だった。負けた方はすべてを失い平等になったのはもちろん、勝った方も国民すべての協力がなければ勝てなかった。だから協力し、犠牲を払った庶民の力が強くなったのである。
同じような興味深い例として、古代のアテナイが挙げられている。アテナイはもともと専制的な国家だったが、平等化を進めて意気の上がった他のポリスに負けて、同じような改革をしたのだ。平等化を進めた結果、アテナイ市民は強力な軍隊となり、勝てるようになった。一方、市民が力を持つようになり、民主主義も発展したという。このように市民全員が従軍の義務を負っている場合は、平等化が進むらしい。しかも、アテナイには累進課税などのさらなる平等化の仕組みもあったし、平時でもGDPのかなりは国家の支出が占めていたという。まるで、今の近代国家みたいな仕組みだったのだ。
だが、アテナイのような少数の例をのぞいて、歴史上ほとんどすべての戦争は平等化に寄与しなかったという。理由は簡単で、ほとんどの戦争は支配者のエリート同士の戦争であり、貧乏な庶民には関係のない戦争だったからである。だから、徴兵制という国民全員が従軍の義務を負う国民国家になってからしか、平等化の例はほぼない。しかも、第2次世界大戦のときのような総力戦になり、「圧倒的な暴力」が行われたときだけ、平等化が進んだという。したがって20世紀の戦争だけがこのような平等化の装置として機能したのだという。ただし、このような平等化を経験した日本や欧米諸国でも、平和が長く続いたいまは不平等が進んでいる。
革命の場合も似ている。革命の例で挙げられているのは、ロシア革命である。ロシア革命では暴力的に地主や資産階級の富が奪われ、平等化が進んだ。銃で脅して、多くの国民を殺して達成された平等だった。ここでも圧倒的な暴力が必要だったのである。
共産主義は他の国にも伝搬し、圧倒的な暴力による平等化が進んだ。中国が代表的で、他にもベトナム、キューバ、カンボジアなどで平等化が進んだ。
しかし、ここでも戦争と同じようなことが言える。このような革命による平等化が実際に起きたのは20世紀だけなのである。それ以前のものは、たとえばフランス革命のような大規模なものでも、平等化は徹底されなかった。暴力が少なすぎたのである。さらに歴史上、不平等に抗議する暴動や反乱が世界のあらゆるところで起きたが、ほぼすべてエリートに鎮圧されて、不平等の解消には全く寄与しなかった。
革命による平等化は、共産主義という政治的にまとまったイデオロギーと、銃を使った国民を大量に殺すという暴力なくしては不可能だったのである。しかも、その平等はその政府が不平等を意図的に抑えているときだけ有効で、いったんタガが外れると、すぐに不平等が復活している。ロシアはソビエト政府が崩壊するとすぐに不平等な社会に戻ったし、中国は資本主義を採用すると、とてつもない不平等社会になってしまった。
戦争と革命は20世紀のみに成果を一時的に出した平等化装置であったが、一方、崩壊と疫病は近代以前にも起きている平等化装置の例である。
歴史上、国家や帝国が崩壊した例は数多くある。ローマ帝国ではローマの貴族に富(=土地)が集中していたが、ローマ帝国が崩壊すると、ほぼ全ての土地を失い、ローマ教皇にお金を恵んでもらうほどに零落(れいらく)してしまったという。中国では帝国が興きては滅びの繰り返しだったが、滅んだ時には国家に依存していたエリートは富を失い、平等化が進んだ。
現代の例としてソマリアが挙げられているのが興味深い。ソマリアはバーレ政権の腐敗がひどかったため、国が崩壊してしまい、いくつかの自治区に分裂した。崩壊前がひどすぎたため、ソマリランドなどの自治区ではかえって生活水準が向上し、平等化が進んだという。
疫病の場合も平等化が進む。ペストがヨーロッパで猛威を振るったときには、住民の人口が何割も減ってしまい、その結果労働力が不足して労働者の賃金が上がり、一方エリートの収入は減って平等化が進んだという。もっとも人口が回復していくと、徐々に不平等は拡大していったそうだ。
疫病でも、このくらい強力で暴力的な疫病でないと、平等化は進まない。(いま蔓延しているコロナウイルスではまったく力不足)。
ただ平等化装置として働くこれら4つの騎士は、どれも全部エリートが没落して貧乏になることにより平等化するのであって、成長の結果平等化するのではないのが残念だ。著者によると、成長した場合は一部のエリートが全部その果実を懐に入れてしまうため、不平等が拡大するらしい。そうすると、基本は貧乏化による平等化ということになる。これだったら平等化されても、なにかうれしくない。
著者によると、平和時に政策等により平等化に成功した例はほとんどないという。土地の公平な分配を目指す政策は何度も世の中に現れたが、失敗した。平和時に成功したのは、16~18世紀のポルトガルと、17~19世紀の鎖国時の日本だけだという。(ここでも日本? よほど日本は平等化しやすい体質なのか?)
この4つの騎士は今後、人類を襲うことは考えづらい状況だという。近い将来に平等化が進むことは見込みにくいようだ。世界的な戦争はいまは起こりにくくなっている。革命が起きることも考えにくい。国家の崩壊も起きにくくなっている。世界的な疫病も起こりにくい(繰り返すが、新型コロナではまったく力不足)。
現代はすでに不平等がかなり進んだ状況にあるが、著者には現代の状況で平等化を進める手立ては思いつかないようだ。新しい平等化の方法が見つからない限り、不平等はさらに拡大するのかもしれない。
なお、付録で述べられている「富の不平等」と「所得の不平等」の違いは重要と思われる。富はひとりの人間がすべてを所有する最大限の不平等があり得る。一方、所得の不平等ではその不平等さには限度がある。所得がなく、食べられなければ、死んでしまうからである。
読んでいて、いろいろ考えさせられる(リンク参照)、良書である。
★★★★★