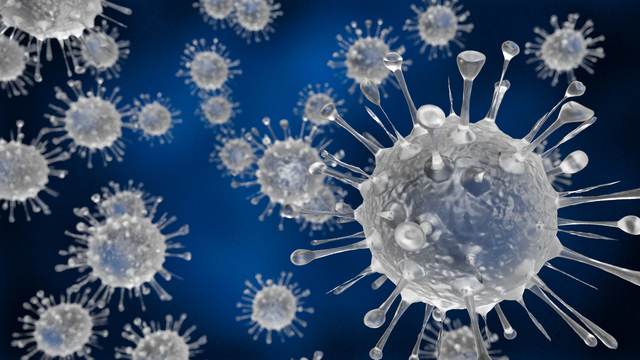自由の命運で、著者たちは日本についてどのような評価を下しているのか、気になるところです。ですが、日本についてはほんの少ししか述べておらず、こんなようなことが書かれてあるだけです。
ーー日本は第2次世界大戦の敗戦までは典型的な専横型の国家だった。アメリカは戦争により完膚なきまでに日本を叩き、軍事的な妄想を一掃した。そして岸信介のようなエリート官僚を抱きこんで強力な国家を作った。自由民主党は一般民衆に政治参加を促し、日本は回廊へ入ることに成功した。
とまあ、非常に簡単な内容にまとめられて、ちょっと拍子抜けの感じすらします。外から見るとそのように見えるのかもしれません。しかし、日本人の我々から見ると、違和感を覚えないでしょうか?
問題は、アメリカが官僚を抱き込んで強力な国家を作ったというところではありません。民衆が政治に参加をしたというところです。この本の理論が正しければ、日本の社会も強力になって、政治に参加をしたことで、国家に足かせをはめることに成功し、日本は自由の回廊に入ったということでなければならないでしょう。でも日本の社会が国家に足かせをかけられるほど強力なものになったのでしょうか。
著者はそう主張したいのでしょう。しかし、実は著者もこの辺はちょっと自信がないのではないのではないかと思われるのです。たぶんそのせいでしょう、日本の社会自体ついてはほとんど何も触れていないのです。ただ単純にひとこと、一般大衆に政治参加を促すことに成功したと。
さて、実際には何が起きたのでしょう。
中村元は日本人の考え方の特徴として、日本人は現在の利益を重視して過去や未来は気にしない、といいます。また抽象的な原理や概念を思考することが苦手だといいます。つまり日本人は自分にとって得になるかどうかで判断して、自由や人権といったそういう原理からは考えないのです。
このことから日本人、ひいては日本社会が、戦争に負けてどのように思考したかは明らかでしょう。日本の社会は軍国主義が優勢だったときには、軍国主義に賛成して追随しました。そのほうが得だっただからです。しかし、日本が負けて、アメリカが日本の支配者になった途端、日本の社会は軍国主義を捨てて、アメリカの求める自由民主国家を支持したのです。その変化について、日本人はまったく躊躇しなかったはずです。なぜなら、そのほうが得になるからです。おそらく過去の自分の発言との矛盾についても悩むことはなかったでしょう。
このような現状追随型の社会が国家に足かせをかけるほど強力とはとても思えないのではないでしょうか。
しかし、おなじ日本人のこの性質から別のことも言えるのではないか、と思えるのです。
日本人は自分の利益を重視するわけですが、そういう意味で非常に個人主義的です。そのせいか、自分を抑える権威というもの対して基本的に反感を持つような性質があります。反権威主義なのです。
考えてみれば、日本では歴史上、中央集権の政府というものはほとんど発生しませんでした。たぶん明治政府がほぼはじめての例ではないでしょうか。このような中央集権国家をつくることができたのは、外国に植民地されるかもしれないという恐怖から可能だったのであり、普段の日本人の性質からは埒外にある特別なことだったのではないか、という気がします。
このような権威を嫌うという性質が、ある意味、国家に対して歯止めになっている可能性があるのではないでしょうか。
最近のコロナ・パンデミックでわかったことは、給付金を支給することが、他の国では簡単だったのに、日本ではとても難しかったということです。それは国民のデータが整理されてマイナンバー等に一元化されていないからでした。
なぜこうなっているのでしょう。政府がバカだからでしょうか。
いや、そうではないと思います。たぶん日本人はその反権威主義のため、政府に個人データを一元化して補足されることをひどく嫌う人たちなのだと思います。なので、わざとこんなややこしいことになっているのではないでしょうか。
日本人は積極的に自分たちのデータをあやふやにして、政府から自分たちへの影響力を減らそうとしているのだとすると、これは一種のサボタージュに近いのだと思います。
世界でも珍しい、こんな特性を持つ国民を治めなければいけない政府は大変です。しかし、もしかしたら、こういう日本だからこそ、日本なりの方法で国家と社会がお互いに牽制し合っているのだと言えないこともない、そんな気もするのです。
そういう権威を嫌う日本人は、専横的な政府は嫌うでしょう。でも、政治的な参加はあまりしないでしょう。こういう曖昧な状態が自分に得だと国民が思ってる間は、日本では自由と民主主義は続くでしょう。なによりメリットがあるうちはアメリカに追随するでしょうからね。
わしは、日本人というのは、いつまでたってもあやふやな状態で、すき間だらけの社会を作り、権威が自分たちのそばになるべく来ないようにする人たちだと思うのです。